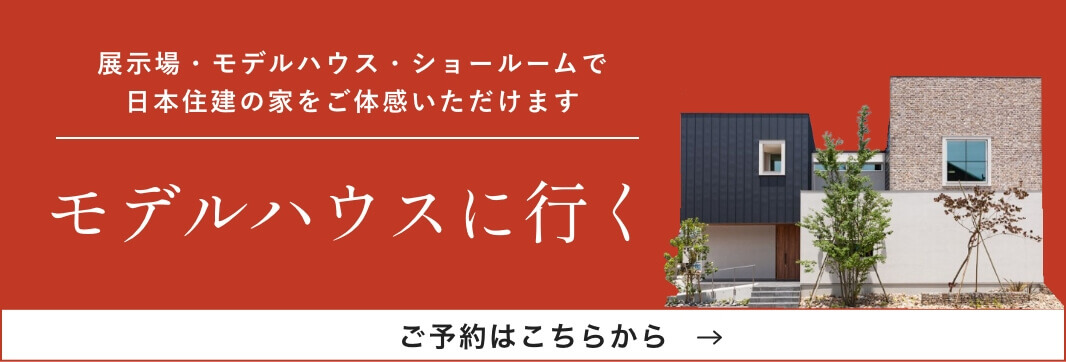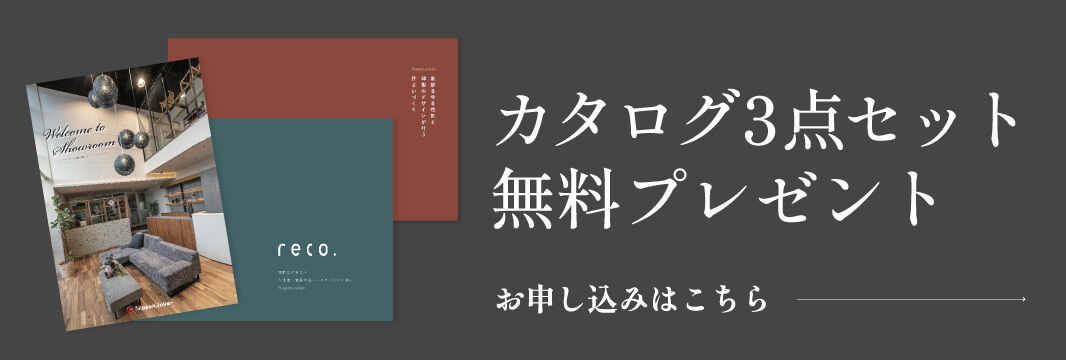木造住宅の強度を支える「許容応力度計算」とは?

木造住宅の強度を支える「許容応力度計算」とは?
「許容応力度計算」という言葉を聞いたことはありますか?木造住宅をご検討の方は、見かけたこともあると思います。この許容応力度計算、安全な住まいを建てるためにはとても重要な計算方法なんです。今回は、この計算がなぜ必要なのか、どんなことをするのかを、わかりやすく解説します。
なぜ許容応力度計算が必要なの?
木造住宅においては、これまで「壁量計算」による計算がほとんどを占めていました。しかしながら、「許容応力度計算」を実施している住宅会社は年々増えている印象です。木造住宅は、地震や風など、様々な力がかかる環境に建てられます。これらの力に耐え、安全に暮らすことが必要ですよね。構造にかかわる部材を細かに分析しながら行う許容応力度計算は、まさにそのための計算方法なのです。
許容応力度計算で何がわかるの?
この計算では、建物の各部材にかかる力(応力)を計算し、その部材がどれだけの力に耐えられるか(許容応力度)と比較します。
「各部材に」というところがポイントです。
これにより、
- 部材が壊れることなく、耐えられる力はどれくらいか…具体的な構造の強度
- 必要以上の部材を使わず、コストを抑えられるか…合理的な設計
といったことがわかります。
具体的な計算の流れは?
- 荷重の算出: 建物にかかるすべての力(自重、積載荷重、地震力など)を計算します。
- 応力度の算出: 各部材にかかる力を、その部材の面積で割って、応力度を計算します。
- 許容応力度の設定: 各部材の材質や形状から、耐えられる限界の応力度を設定します。
- 比較検討: 算出した応力度が、許容応力度を超えていないかを確認します。
許容応力度計算のメリット
- 安全性が高い: どこまで耐えられるかを計算するので、建物の強度がしっかりと保証されます。
- 耐震等級3: 詳細分析に基づく耐震等級で、高い耐震性能を証明できます。
- 構造の最適化: 過剰な柱や壁を設けることなく、必要な強度を確保できるので
コストを抑えることができます。
許容応力度計算のデメリット
- 専門知識が必要: 複雑な計算のため、専門的な構造の知識が必要です。
そのため、多くの住宅会社が外部にお金を払って依頼しており、コストがかかるといわれています。
日本住建の許容応力度計算
日本住建では、全棟自社スタッフが許容応力度計算を行っています。住宅会社としては、かなり珍しいのではないでしょうか。
自社スタッフによるメリットは、外注コストの削減かと思われがちです。
しかし実際は、「構造計算士がお客様の要望にタイムリーに触れられること」そして「ノウハウの蓄積ができること」です。
プランを担当する設計士と、許容応力度計算を行う設計士が、常日頃から密接にコミュニケーションをとれる環境にいることで、お客様の想いを汲み取ることができる、ということが非常に重要だと考えています。
「この間取りで強度が成り立つかどうか」ではなく、「こんな暮らしをしたいお客様の間取りを叶えるためには、どこに柱や耐力壁が必要か」「自由度を持たせながら強度を保つには、どこに柱や梁を設けるのよいか」など、プランを担当する設計士と一緒になって考える。これこそが社内で許容応力度計算を行う最大のメリットです。
まとめ
- 許容応力度計算は各部材の強度を細かく調べる構造計算方法で、安全性が高いだけでなく、合理的・経済的な設計にも有効な計算方法です。
- 日本住建では、社内設計による全棟許容応力度計算を実施しています。
この動画では、許容応力度計算について、さらに詳しく解説しています。
気になった方は、こちらの動画をチェックしてみてください。
https://youtu.be/15tdqAim_5E?si=qIdV9HajEvpVmrDB
また、この動画が役に立ったと思っていただけましたら、👍やチャンネル登録もお願いいたします。
日本住建は1975年の創業以来、安城市・岡崎市・西尾市・豊田市など三河地域を中心に地域密着型の家づくりを行ってきました。
「全棟許容応力度計算による耐震等級3+制震ダンパー標準採用」に加え、「高性能」と「デザイン」を両立する注文住宅をご提供しています。ぜひお気軽にご相談ください。
展示場・モデルハウス
日本住建の家をぜひご体感ください